




 七峰
七峰こんにちは道具担当七峰です。今回は西欧の子どもたちのトラウマ、イラクサを使ったお仕置きについて見ていこうと思います
そもそもイラクサってなんやねん
まずはイラクサのお仕置きシーンから。
『蒼い衝動』(原題 Les exploits d’un jeune Don Juan, 1986)※R15
ファサファサしていて痛くなさそう…?
いえいえ、そんな生易しいものではありません。注目すべきは、カーの女性が黒い手袋をしてイラクサを持っている点。
では、さっそくイラクサという植物から見ていきましょう。
イラクサ(英語名 ネトル nettle)は日本にも野生していますが、今回主にお話しするのは、北米や北部ヨーロッパに生えているセイヨウイラクサについてです。とはいえ、イラクサなんてあまり日常で触れることも少ないですね。遠目で見たヴィジュアルは決して特徴的なわけではなく、ちょっと葉っぱがとげとげしてるかもなあ、くらいの形です。
しかし、その漢字表記を見れば、一瞬でイラクサの戦闘力がわかります。イラクサの漢字表記は2種類存在します。一つ目は古語の和名に漢字を充てた表記。
刺草
「いら(刺)を持つ草」ということです。そしてもう一つが中国から来た漢名。
蕁麻
何だか見たことある漢字……
そう、蕁麻疹(じんましん)の蕁麻です。
 七峰
七峰普通に毒々しいわ
そう、この凶悪な植物は、その茎でお尻を叩くことで
トゲ
かぶれ
2つのダメージを与えられる、恐るべきお仕置き道具なのです。
ちなみに、イラクサは、現代中国語では咬人猫と書きます。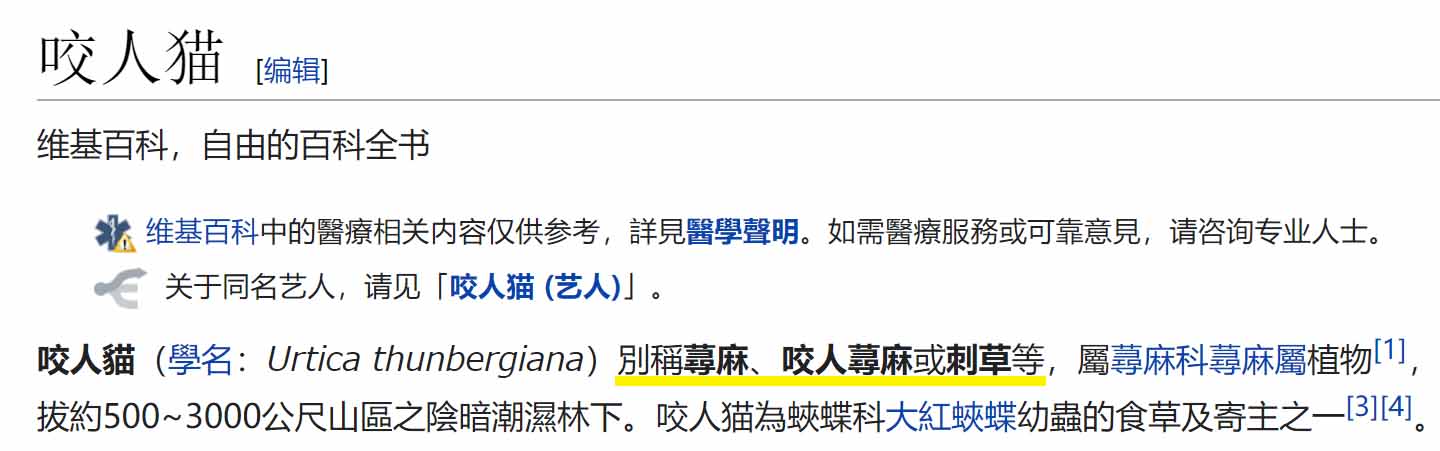
噛んでくるネコ……かわいい……
 七峰
七峰なぜイラクサのお仕置きが強力なのか、化学的なことはわからないからエマお願い!
 十束
十束任せて!
先ほどの写真を再度見てみましょう。イラクサは茎や葉に刺毛(しもう)と呼ばれる棘を生やしています。これは固くとがっているバラの棘とは少し違った雰囲気ですね。

この刺毛は、先端がガラス管のような仕組みになっており、ものに触れると折れて内部の液体が流れ出ます。
 十束
十束これがパンと人の肌に叩きつけられると、先端が割れた刺毛が大量の注射器となって、化学物質満載の液体を体に送り込むわけね
なんでこんなに攻撃的な構造をしているのかというと…… もちろん植物が捕食動物から自分の身を守るためです。奈良公園のイラクサは、シカから身を守るために刺毛の密度が高いとの調査結果もあります。
刺毛は葉や茎にあって、外敵から身を守るための手段と考えられるのですが、それでも動物に食べられてしまうと、刺毛が増えることが観察されています。シカのいる奈良公園内のイラクサは刺毛密度が他地域に比べて数十倍〜数百倍にもなり、シカが嫌うことが明らかになっています。
ネトルの植物学と栽培 https://www.medicalherb.or.jp/archives/178554
また、
植物って不思議ですね。
ソ連の映画『うこそ、あるいは立ち入り禁止』では、感染症の仮病を企んだ少年たちがすっぽんぽんでイラクサの草むらに飛び込み、全身が腫れてまんまと成功する一シーンも。
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (1964)
 十束
十束なお、全身痛くて、もはや仮病じゃない模様
おバカ可愛いっ
さて、ここまでイラクサは凶悪なお仕置き道具だ! とアピールしてきました。しかし、実際のところは人類が考案した人工の懲罰具には叶いません。
 七峰
七峰いくら化学反応を持つと言っても、そりゃ鞭の方が威力強いでしょう
実際、イラクサが罰として存在感を発揮するのはせいぜい中世まで。それも公的な刑罰ではなく、民間のお仕置きアイディアの一つくらいの立ち位置です。
一方で、化学的な反応を引き起こすことで、人々はそこに不思議さ、神秘さを見出してきました。
ドイツの民間伝承やグリム童話に登場するおばさん精霊 フラウ・ホレ は、糸紡ぎの仕事をサボった娘をイラクサ叩きのお仕置きをするためにやってきます。一方で、きちんと仕事をした娘にはイラクサを一本置いていくとのこと。
 十束
十束う、嬉しいのかしらそのプレゼント
イラクサによるお仕置きの活字の作品も探したかったのですが、こちらはなかなか見つからず…… 実写ドラマで複数スパシーンがあり、原作でもそこそこ恵まれている『アウトランダー』の一部を引用します。未遂ですが。
 七峰
七峰『アウトランダー』はとある女性の過去へのタイムスリップ物
夫による妻へのお仕置きが常識(むしろ責務)の時代に飛ばされたクレアは、お仕置きの認識について、その時代での夫ジェイミーとちょいちょいバトりますー
「ガスコーニュ地方の農民は、不実な女房をイラクサで打つ」彼はとがった葉を下にして、私の胸を頭状花で軽くこすった。チクっとして、息をのんだ。肌の上にまるで魔法のようにかすかな赤い斑点が浮かんだ。
「きみはおれにそうさせたいのか? そうやってきみを罰しろと?」
「もしあなたが……そうしたいのなら」
しかし、イラクサのお仕置きは執行されず、なぜかエモい雰囲気になってそのままS●X。しかし事後、ジェイミーの手はイラクサを握っていたことで腫れており ……
アロエの茎を折り、肉厚の葉を裂いて、ジェイミーの掌のみみず腫れに、冷たいグリーンのジェルを塗り広げた。
『ジェイミーの墓標Ⅱ(アウトランダー5)』ダイアナ・ガバルドン、訳 加藤洋子
「良くなった?」
「だいぶ」ジェイミーは手を握り、顔をしかめた。「まったく、イラクサの棘ってやつは、痛いのなんの!」
「そうでしょうとも」ボディスの襟を開いて、アロエのジェルをそっと胸に塗った。冷たさで痒みがすっとひいた。
「あなたが私の頼みを届きくなくてよかった」ちかくで花を咲かせるイラクサの茂みにちらっと眼をやった。
かれはにんまりし、よいほうの手でわたしの尻を叩いた。
結局お尻叩くんかい!
ちなみに……
お仕置きにイラクサを利用する理由として挙げられること
苦痛を伴うものの、一時的なもので棒などと違って外傷や後遺症が発生しにくいということがあります。
 七峰
七峰な、なんていうか、物は言いようね……
バーニョ・デ・オルティガ(Baño de ortiga)
「イラクサ風呂」の意味を持つこの刑罰は、南米アンデス地域(エクアドルやペルー)の先住民コミュニティにおいて行われてきた「先住民の正義(justicia indígena)」と呼ばれる罰の一つです。
 十束
十束先住民の正義、とは村人の合議によって独自に行われる懲罰のことで、
エクアドルでは2008年憲法で「先住民司法の権利」が正式に認められており、一定の範囲内で国家もその裁きを尊重するよう明文化されているんです
バーニョ・デ・オルティガ窃盗などの犯人などに課されるもので、犯人は裸にされ、公衆の面前で鞭で尻を叩かれたり、イラクサで叩かれたり、冷水をぶっかけられたり、それを繰り返されたりする罰です。イラクサ打ちは罪の重さによって20~200発まで様々です。
先住民の正義としてはメジャーなもので、探したら画像や動画が比較的多くみられるかと思います。流石に全裸ではなく、男性はパンいち、女性は+ブラであるものの、容赦なくビシビシと打たれる様子が分かります。
ちなみに、これを書いている2025年においても、スマホで取られた最新の処罰映像が上げられ続けております。うへえ。世界は色々だなあ。
一方でこんな動画を見つけました。
ロシアのとある村議会において「詐欺師議員」に対して公開のイラクサによる尻叩きの刑が執行されました。彼は恥ずかしい服装をさせられた上に「詐欺師議員」の紙を背中に貼り付けられ、イラクサの束で住人から3発ずつ叩かれて行きます。
 十束
十束チャンネル主、この叩かれている議員じゃない
 七峰
七峰服の上からのイラクサ叩き、
無意味!
 十束
十束そこ!?
古代ローマの風俗小説『サテュリコン』には、インポテンツになった主人公エンコルピウスに対し豊穣神プリアポスの女祭司が「熟したイラクサの束で尻を叩く」療法を施します。
古来からイラクサで裸体を叩くことが不能、不妊の治療に使われてきました。
実際のところ、イラクサはその刺激性から世界の各地で伝統的に一種の興奮剤として使われてきました。これを
ウルティケーション(urtication)
といいます。ウルティケーションはサウナのように血行を促進し、それは何らかの効能をもたらしそうな感じはします。
19世紀の医師ミリンゲンは、アーティケーションが麻痺や昏睡の治療において有効であることを説いています。ただ、あくまで民間療法の域を出ず、「打たれるときの刺激による快感」を原動力としているので、患者の精神状態、そして “嗜好” に依存するものでしょう。
 源
源そもそも、イラクサじゃなくても、普通のセルフおしりペンペンでエブリデイ健康ライフなのです
ウルティケーションに関する細かい話は、以下のページ『体罰の歴史』の 第1部:鞭打ちの心理学 第4章:痛みの治癒的および医療的効能 もご参照ください。


じゃあイラクサでお尻を叩くのは、お仕置きに常用されていたのかと言うと……
それはちょっと難しいんじゃないかなぁ、というのが正直なところ。
少なくとも、化学物質が絡んでくるので、キーに対するダメージコントロールが自力ではとても難しい。あまり愛のあるお仕置きではないですね。そのかぶれ方は、全くもって美しくなく、皮膚はひどい虫刺されのような状態になります。
「nettle spanking」とかで検索したほうが手っ取り早いと思いますが、少なくとも管理人は見るだけで萎えます。
(とはいえ、映像・画像・文章の媒体問わず、ある程度のイラクサ・ポルノがあるのは、一定の需要があるというわけですが)
さらに、イラクサは下手したらカーの方も手がかぶれるという、まさに文字通りの諸刃の剣。写真やイラストでは、スパンカーは手袋をしていることも多いです。逆に言うと、葉っぱのついた植物を持っていて、手袋をしていたら、それは十中八九、イラクサです。
 七峰
七峰カー視点でもキー視点でも七面倒くさい道具だなあ……
やはり現実的な体罰というよりは、フィクションの世界(現実でのプレイを含む)で使われるものとして考えた方がよさそうです。
イラクサは白樺のように鞭として使うことも可能ではありますが、その形状や強さを考えると、物理攻撃力は大したことはありません。イラクサでお尻を叩くことで、かぶれを引き起こして痛痒いダメージを与えることができるわけです。
あれ、叩く必要なくない?
そうなのです。触れていればいいので、叩く必要はないのです。とはいえ、19世紀イギリスでの “大人の” 社交サロンなんかではイラクサのスパンキングプレイが流行ったりもしていました。それは、イラクサのヒリヒリした刺激が性的な興奮を引き出すからとも思われます。
そして、もっと陰険なお仕置きもあれこれ存在します。たとえば、下半身を裸にして、イラクサを敷き詰めたイスに座らせるとか、パンツの中にイラクサを詰めるとか。もっと極端なものでは、箱にイラクサを敷き詰めて、そこに素っ裸にした女性を突っ込むとか……

お尻叩きの後に、コーナータイムではなくネトル椅子に座らせる方法も可能ですが、エロチカ作品ではやはりスパンキングとは別に、すっぽんぽんでイラクサに突っ込む方が過激でその筋の人々には受けがいいのかなと。
 七峰
七峰そ、そこまで行くとウチのテリトリー外になってしまいますよ。なんだかんだで、触れるのが一瞬である「叩く」と言う行為が、コントロールしやすいので、プレイとして一番楽しみやすいのかもしれませんね

「オークとイラクサの日(Oak and Nettle Day)」@イングランド
「オークとイラクサの日」は、5月29日にノッティンガムシャーで行われる伝統行事である。この日はチャールズ2世の王政復古と彼の忠誠心を記念するもので、少年たちはオークの小枝とイラクサの束を手にし、オークの葉を身につけていない者に対して、手や顔をイラクサで打つ罰を与える。かつては腐った卵を使った罰もあった。オークの葉は、チャールズ2世がボスコベルのオークの木に身を隠して逃れた故事にちなむ忠誠の象徴である。ちなみに、イラクサ叩きだけではなく、お尻をつねる罰ものあるので、Pinch-Bum Day とも呼ばれる。
帝政期ロシアとイラクサ
ツァーリ政権下からソ連期にかけて、田舎の子供にとって「イラクサで叩かれる」恐怖は現実味のある脅し文句だった。ベルトで叩くことと、イラクサの束で叩くことが
フランスの慣用句
フランス語の表現 「mettre aux orties」 は、直訳すると「イラクサの中に投げ入れる」「イラクサの上に置く」という意味だが、ないがしろにするという意味を持つ。
ドイツの慣用句
「自分をイラクサの中に置く(sich in die Nesseln setzen)」は「厄介ごとに首を突っ込む」「自ら墓穴を掘る」という意味で使われます
『ヴァレンティヌスの選択』エリザベス朝期の小説
:エリザベス朝の艶笑詩で、女性に振られた男が自慰具(ディルド)に嫉妬する滑稽な内容。この中で、秘密を漏らすお喋りな若者への警告として「お前はイラクサで叩かれる羽目になるぞ」と脅す場面がある。
“Thou wilt be whipped with nettles for this gear if Cicely shew but of thy knavery here.”
マルキ・ド・サドの『ソドム百二十日』
イラクサでの鞭打ちを行う描写がある。イラクサとヒイラギで血まみれになるまで叩いたという記述がある…… 打つ方が大変じゃないか……?
ルイスェーニョ族のイニシエーション
スペイン人宣教師ボスカーナの民族誌『チニグチニッヒ』(1830年代刊)には、南カリフォルニア先住民の少年が成人の儀式でイラクサの鞭打ちによって体を腫れさせた後、凶暴なアリの巣に寝かされて、それを耐え抜く、という記録がある。
アンデルセンの童話『野の白鳥』
この物語で主人公の王女エリサは、魔女によって白鳥に変えられた11人の兄たちを人間に戻すため、言葉を発さずにイラクサで糸を紡ぎ、手が腫れ上がりながらも鎖帷子を編むという苛酷な使命を課せられる。本当は怖い童話にありそう。
セネカのイラクサ
フランス領コルシカ島には、古代ローマの哲学者セネカ(紀元1世紀)が島流しにされた際の伝説が残されている。彼が島流し中、地元の女性たちに対して不埒な行為を試みたことに対し、報復として全裸のままイラクサの茂みに転がされたというものである。この逸話は現在もなお島内で語り継がれており、イラクサが「セネカのイラクサ(ortie de Sénèque)」と呼ばれる由来ともなっている。